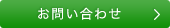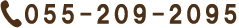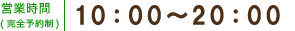東洋医学的 腹痛について
前回からだいぶ間が空いてしましましたが

今回は東洋医学的からの視点から見た腹痛について書いていこうと思います。
皆さんの日常では西洋医学的な考えが身近にあると思いますが
今回これを機会に東洋医学にもぜひ触れてみてください

東洋医学的には、
心窩部周辺(みぞおち周辺)に起こる痛みを『胃脘痛』
臍周辺に起こる痛みを『臍腹痛』
下腹部に起こる痛みを『小腹痛』
脇腹に起こる痛みを『少腹痛』
といいます。
1、 胃脘痛
心窩部周辺に起こる痛みで、東洋医学的な臓器では胃の病変としてとらえます。
東洋医学の概念では、胃は水穀(飲食物)の受納(受けて納めること。受け入れること。)
と腐熟(堆肥(たいひ)などがよく発酵して腐ること。)を主るといわれ、
飲食物を受け入れて一時保留し、消化する機能を持つといわれています。
この胃の考えは東洋医学も西洋医学も似ていますね
また、胃は通降を主るともいわれていますが、これは消化した飲食物を小腸に移動させた後、消化・吸収を表す言葉です。
従って、東洋医学的な胃の機能が低下すると食欲低下、心窩部の膨満感、胃脘痛(みぞおちの痛み)などの症状が現れます。
1) 寒邪犯胃の胃脘痛
漢字がならんでいて、いかにも難しいような印象を受けますが、

意味は漢字の通りで、
身体が寒邪(寒さ)による侵襲(生体を傷つけること)を受けた場合や、
冷たいものや生ものなどを過食した場合に起こる心窩部の痛みのことをいいます。
主要な症状は
胃脘部の強い痛みで、圧を加える(手などでさすったり抑える)と不快感が起こります。
痛みは冷刺激により増強し、逆に温めると軽快します。
温かい飲み物を好む傾向にあります。
2)食積(食滞)の胃脘痛
飲食の不摂生(健康に気をつけないこと)や暴飲暴食などにより、胃に食積(食滞:食物が停滞)が生じておこるものです。
暴飲暴食以外にも、東洋医学的な胃と脾が弱っている人が、消化の悪いものを食べた場合にも起こる。
主要な症状は、
胃脘部の張ったような痛みや圧を加える(手などでさすったり抑える)と起こる不快感、
厭食(食欲、摂食量低下)、噯気(げっぷ)、嘔吐(吐くと疼痛が軽減する)、
呑酸(酸っぱいものがあがる)などがあげられます。
次回も胃脘痛についてかいていきますね!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
高田馬場駅、目白駅から徒歩6分
デスクワークや家事が原因で起こる肩こり、腰痛はリムス鍼灸整骨院まで。
自費治療、鍼灸治療、整体などの施術もできます。
健康保険、交通事故治療、自賠責、労災、各種保険対応しております。
リムス鍼灸整骨院
〒東京都豊島区高田3-32-3メイスンビル1F ☎03-6912-6467
診療時間 平日 11:00〜22:00 (最終受付 21:00)
土日 11:00〜19:00 (最終受付 18:00)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□